受験生が5~6月にやる勉強
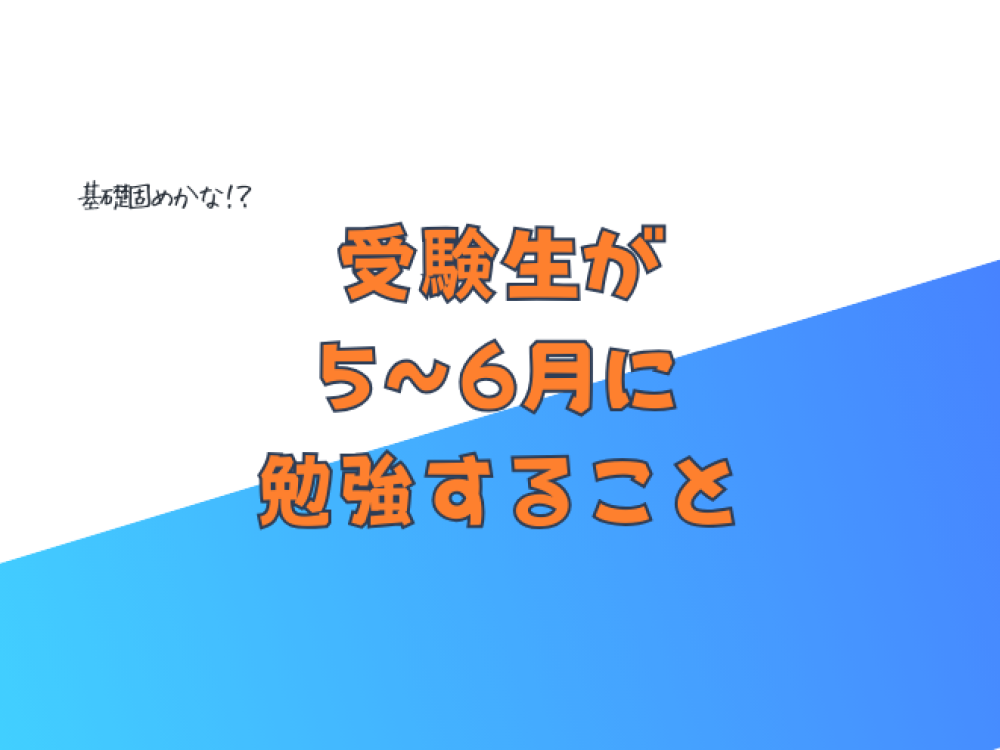
こんにちは。こんばんは。
学習塾 Study atの柄澤です。
今回は、「受験生が5~6月にやる勉強」についてお話しします。
受験生といっても、中学受験、高校受験、大学受験と様々な方がいます。今回は、高校受験、大学受験を控えている受験生に向けた内容をお話ししようかと思います。
①志望校を決める
志望校を決めるというのは、勉強です。なぜなら、志望校を色々調べて知識を付けて、決めるから。これは、勉強ですね。
高校受験、大学受験どちらの立場の方も、この時期はまずは志望校をはっきりさせていくことかなと思います。
もちろん、無理に決める必要はありませんが、志望校を決めて勉強している場合と、志望校を決めずに勉強している場合では、結果が全然変わると思います。
なぜ、自分は志望校が決まってないけど、周りの子で志望校が決まっている子がいるのか?何が違うのか?
それは、「決める」という点が大きな違いかなと思います。
志望校が決まっている子は、そこまで深く物事を考えて、決めている子は少ないでしょう。けど、家から近いから、地域で一番学力レベルが高いから、大学進学率が高いから、専門学校に進学する子が多いからなど、思ったより単純な理由で高校、有名企業への就職率が高いから、技術系に進みたいから、トヨタ系に進みたいからなど
自分で「決める」ことは、自分に責任が付いてきます。多くの方は、この選択をしたときに不利になったり、不都合な状況になったりと不安になります。しかし、もっと素直に決めていくことが、大切だと思います。
②逆算して何をしなければいけないのか、何をするべきなのかを知る。
入試直前で基礎内容をやりますか?
やらないですよね。
入試直前では多くの方は、過去問をやったり、その過去問で解けなかった問題を解くために必要な知識を身につけたり、します。
何も考えずに勉強することは、入試に近づいてきたときに焦ることになります。
あれも、これもやらないといけないことが増えてきます。その結果、学力の成長が間に合わない事態に陥り、受験校のレベルを下げたりする状況になります。
もちろん、きちんと計画を立てて、勉強した結果、成績が上がらないという状況もあると思います。しかし、何も考えていない状況とは違い、勉強すべきことは合ってますが、勉強のやり方、いわゆる復習のタイミングや、1回の勉強の進め方がダメだったりします。
勉強というのは、内容とやり方の2つのことを考えなければいけません。
では、ここからは高校受験に向けた内容をお話しします。その後、大学受験に向けた内容を話します。
高校受験に向けて、5~6月にやるべき勉強は基礎固めです。
中学3年生の内容が終わっていないので、中学3年生の内容を含め、中学1年生~中学2年生の学習内容を復習していく必要があります。
中学3年生の学習内容は定期テストの点数で判断できます。定期テストは6割が平均となるように作られており、内容は基礎内容がメインとなります。
入試レベルの基礎固めとなると、定期テストでは8割以上は目指すべきと考えます。
定期テストレベルで8割以上では、基礎だけじゃないと感じる方も多いと思いますが、それでは入試レベルの基礎のレベルには到達できていません。
また、「自分ができない問題=基礎ではない」と判断する方が多いですが、これは間違いです。
また、数学でいうと、文字式の計算は基礎内容だけど、図形問題や関数問題、連立方程式の利用などは基礎ではないと判断する方がいますが、これも間違いです。
国語では言葉の決まりの内容、漢字
数学では、中1~2年生の計算内容→方程式→関数→図形の順で
理科では、第二分野の暗記系(生物、地学)を先に復習
社会は、歴史から
英語では単語→新研究の最後に1800単語あるのでそちらを1から覚えていく。
まずは、このあたりからやるといいですね。
次に大学受験に向けた内容です。
大学受験では、5~6月の時期は、受験科目の中でメイン科目の基礎固めです。
大学受験では、受験科目が受験校によって様々です。
国公立大学を目指す方は、受験科目が膨大にあります。二次試験も含めて、各科目の総合点数に対しての割合を計算しましょう。
その結果、優先順位を決めることができるので、上位3科目から優先して勉強を進めることがおすすめです。
私立大学は3科目で受験できるところが多いと思います。共通テスト利用を利用する場合であれば、そのも含めて優先順位を決めて勉強する科目を絞っていきましょう。
この時期は、高3生は部活が終わるころで、勉強時間を増やすことができるようになります。どの科目も満遍なく勉強したい場合は、どの曜日にどの科目を行うのかを決めていきましょう。
それに含めて、次の日は復習、3日後に復習する習慣を作るといいですね。
付箋を使って復習をするタイミングをメモしていくことが大切です。また、問題にもいつ勉強したのかと評価を付けていくことが大切です。
国語であれば、古文単語、文法
数学であれば、1Aの基礎~標準内容=傍用問題集(4プロ、サクシードなど)もしくは基礎問題精講など
社会、生物、物理、化学などの学校の問題集で基礎を復習して、知識の穴を埋めていく。
英語は英単語と文法→すでに終わりそうな方は英文解釈(構文演習)を進めましょう。
6月の終わりに、どのような状況が理想なのかをきちんと明確にしましょう。
今回は以上です。
